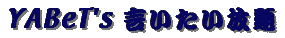
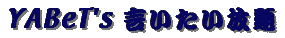
| 情報の渦の中に埋もれる必要な情報---マーガリンが売られ続けるアメリカ | |
|
にわかに自炊を始めたとたんに「食」にうるさくなったわけではないが、そもそも栄養とは何だろうと常々思っていたのは確かである。まがりなりにも農学部を卒業した身の上に、百姓のせがれときては、否が応にも無関心ではいられない・・・と言いたいところだが、まあはたから見て僕が食べ物に気を使っているようには見えないだろうことに反論はしないけれど。 誰もが小さい頃から「これは体に良いからたくさん食べなさい」とか「これはあまり食べちゃいけない」とか、耳にタコができるまで聞かされてきただろうけれど、栄養学を「人間にとって最も望ましい食事」、言い換えれば「最も病気から遠ざける食事」を探す学問だと解釈すれば、その全体像が明らかになってきたのはせいぜい1980年代に入ってからで、さらには栄養とは何かを科学的に説明出来るようになったのはつい最近の1990年代のことである。これが意味していることは、長く体に良いと信じられてきた食べ物の中には実はそうでないものが含まれていて、すでに現代の科学によってそれが解明されているにも関わらず、一般に伝えられていないものが巷に溢れていると言うことである。 動物性脂肪は体に良くなくて植物性脂肪は体に優しいという話を耳にしたことがある人は多いと思うが、なぜ動物性脂肪は体に良くないのか。かいつまんで言うと、それを構成する主な脂肪酸が飽和脂肪酸と呼ばれるもので、植物性脂肪を構成する不飽和脂肪酸が低い融点であるのと対照的に、飽和脂肪酸の融点は44℃〜84℃と極めて高いことが体に悪い原因と考えられている。人間の体温はだいたい37℃だから、体の中でこれらの飽和脂肪酸は当然のことながら固体状をなしていることになる。 人間の血液は基本的に水で出来ているから、固体状の脂肪とは相容れず、しかたなく人間の体はこれを細かい粒に砕いて血液の中を循環させているけれど、この脂肪の粒同士はお互いにくっつきやすく、おまけに血液の中では赤血球同士をもくっつき合わせてしまう糊のような働きをするものだから、それがどれだけ体に悪さをするのか、まあ想像に難くない話である。 この「体に良くない」動物性脂肪の牛乳から作られるバターに代わるものとして、現在では植物性脂肪由来の「マーガリン」が広く浸透している。そもそもマーガリンは、19世紀の末にバターの代用品としてフランスでつくられたもので、生活必需品ではあるけれども高価なバターに代わる安価な代用品の必要から、ナポレオン3世が代用バターの発明を懸賞募集したことによって考え出されたものである。「margarine」はギリシャ語のmargarite(真珠)を由来とする言葉で、真珠のように美しい油のかたまりという意味があり、特に植物油を原料として作られていたわけではなかった。現在では健康志向の高まりで、マーガリンと言えば植物性脂肪を原料として風味を加えるために乳製品を使っている製品が出回っているようだが。 さてこのマーガリン。先に述べたように動物性脂肪の特徴は低温(といっても体温程度)で固まりやすいことで、植物性脂肪は固まらないことであったが、はて、なぜに固形状なのだろうか。 マーガリンはどのように作り出されるのか。簡単に説明すると、植物油を金属の触媒の入ったタンクに入れて120℃から210℃の高温にした状態で圧力を加えて水素ガスを送り込む。すると、植物油を構成していた不飽和脂肪酸が動物性脂肪と同じ成分の飽和脂肪酸に変化し、室温で固体状のバターのような油脂が出来る。しかし、ここで100%の効率で飽和脂肪酸に変化することはなく、不飽和脂肪酸のままのものが残り、さらにこの一部が自然界には存在しないトランス型と呼ばれる奇怪な形の不飽和脂肪酸に変化する。自然の脂肪酸はシス型と呼ばれる形をしていて、この形が脂肪酸の栄養としての最大の役目である我々の体の細胞膜を構成するときに大きな意味を持つ。 つまり、マーガリンに含まれるトランス型の不飽和脂肪酸は、細胞膜を構成することができないばかりか、もともと自然界に存在しない物質であるから代謝が困難なために酵素が多く使われて、シス型不飽和脂肪酸の正常な代謝の能率をダウンさせることになる。要するに、マーガリンは動物性脂肪由来の飽和脂肪酸に勝る不飽和脂肪酸としての機能を全く果たさないばかりか、この人工的な化学物質は、LDLコレステロール(悪玉)の血中値を高め、HDLコレステロール(善玉)の血中値を下げ、リポプロテインaの血中値を高めることが現在では広く知られている。リポプロテインaは、心筋梗塞と脳卒中の引き金となる単独の危険因子として知られているものだから、このトランス型脂肪酸の極悪非道ぶりが知れようというもの。ちなみに、同じ方法で作られるショートニングも、同様に危険なトランス型不飽和脂肪酸が含まれていることは言うまでもない。 我が身の危険に敏感なドイツではすでにマーガリンの製造販売が禁止されているが、ふと周りを見渡して、ここアメリカではなんの違和感もなくマーガリンが売られていることに気が付く。これだけ証拠として明らかなものが出揃っている現代において、この泰然自若ぶりはどうしたことだろう。まるでタバコの「健康のため吸い過ぎには注意しましょう」的な滑稽な見出しの、「低トランス型不飽和脂肪酸」とうたった開きなおったマーガリンも出現しているが、果たして第2のタバコ訴訟に発展する前に対策を講じてほしいものだが。 なぜ、「マーガリンには危険な面があるけれど、リスクを知りながら自己責任で食べて下さいね」という情報が消費者の耳に届かないのか。かつて1991年にアメリカの農務省がデータに基づく「何を食べるべきか」という事を表現した「食のピラミッド」を発表しようとしたとき、突然待ったがかかり翌年の春まで発表が遅れた事がある。これは「肉や乳製品はそれほど食べなくても良い」とするこのレポートに反発したこれらの産業から圧力がかかり、うやむやにされそうになったためだと言われている。 様々な情報が飛び交う自由の国アメリカで、しかし本当に必要な情報こそが不自由な思いを強いられているのは、これも「自由経済主義」の避けがたい一面なのだろうか。アメリカの後を追うようにして「自由経済」をものにしてきた日本でもまた、いま平然とマーガリンが売られている。 |
 BACK
BACK 
| 野茂英雄という大リーガーの魅力 | |
|
Hideo No-No! 2001年のメジャーリーグのシーズンが始まってまだ2試合目のマウンドに、ゲームオーバーのその瞬間、驚喜の輪が出来た。その輪の中心には、普段の仏頂面からは想像もつかないが、しかし彼特有の「子供のような笑顔」の野茂がいた。この野茂の笑顔を見たのは何年ぶりだろう。よかった。野茂はまだ昔の笑顔を持った大リーガー、『Hideo Nomo』だった。 ホームラン量産球場とさえ呼ばれるクアーズ・フィールドを本拠地とするロッキーズを相手に、前年の新人王の勢いそのままにロサンゼルス・ドジャースのエースとして神懸かり的なノーヒット・ノーランを成し遂げた、1996年9月17日から5年の月日が流れた。野茂英雄は、1997年のシーズン終了後のひじの手術が影響してか、その年にメジャーリーグ史上最速の奪500三振を記録した速球に陰りを見せて、その後は生彩を欠いて球団を転々とした。そして、昨年まで在籍したデトロイト・タイガースからFAを行使して、21世紀となった今年、1年契約でここボストンにやって来た。レッドソックスは彼の5番目の球団となる。 そして野茂英雄は、2001年4月4日午後10時17分のその時、ボルチモア・オリオールズを相手の敵地カムデン・ヤーヅで、両リーグでノーヒッターとなった史上4人目のピッチャーとして、新天地ボストン・レッドソックスのデビュー戦を華々しく飾った。レッドソックスのベンチでは、あの日ルーキーとしてロッキーズでその瞬間に悔し涙を流した、いまや2億円プレーヤーのDante Bichetteが、同じピッチャーの2度目の偉業をその目に焼きつけていた。そして、レフトを守るTroy O'Learyのグラブに最後のボールを打ち込んだバッターこそは、5年前には野茂の僚友としてドジャースに名を連ねたDelino DeShieldsだった。 野茂がレッドソックスに入団したのには、ちょっとした裏話がある。まだ25歳のルーキーである大家投手に、大きな期待を寄せているレッドソックスのジェネラル・マネージャーは、どことはばからず大家投手が尊敬するピッチャーとして名を挙げる野茂投手のそのピッチングを目の当たりに見せるというまさに活きた教育を実践することで、彼をさらに成長させようという魂胆があったそうだ。そこで獲得を企んでいたMike Mussinaをヤンキースにかっさらわれるとすぐさま、FA宣言していた野茂投手はデトロイトから1年契約で獲得されたのだった。 このちょっと複雑な事情の絡んだオファーに、野茂はむしろ喜んでサインし、ボストンに乗り込んできた。彼の尊敬するピッチャーこそは、ボストンのエースであるペドロ・マルチネスであり、同じチームでワールドチャンピオンを目指せる野球人としての喜びが、単純にお金のことやしがらみを上回ったようだ。そして、ペドロに身近に接してさらに野茂は彼に傾倒し、いまや年下の彼に頭を下げて彼の投球術を教わっているそうだが、ペドロの「まずはストレート」というその教えが、この日の大仕事に大きく貢献したことは疑いない。またペドロも、普段の非番の日は試合途中にベンチに現れるや、ベンチの右端の足場に横たわってだらあっと応援しているのだけれども、この日はいつものように試合途中にやって来て5回を終わったベンチに一歩足を踏み入れたとたんに野茂の集中ぶりを敏感に察知し、その雰囲気を壊すまいと、さっときびすを返して控え室に戻ってしまったそうだ。大人(たいじん)は大人を知るのである。 9回裏1アウトまで、3つのフォアボールとエラーのランナーを出しただけで依然一つのヒットも得点も許していない状況。ここで、次打者の打球はふらふらあっとセンターのはるか前方へ上がるポップフライとなった。それまでセカンドを守っていたStynesの怪我によって、後半から守備についていたLansingはしぶとく球に飛びつき、頭からグラウンドに落ちて回転しながらも捕球した球を離さず、ファインプレーを演出して大記録達成への望みをつないだ。 しかし、この場面の後、多くの往年のレッドソックスのファンは、嫌な予感を抱いたそうだ。 レッドソックスで最後に達成されたノーヒット・ノーランは1965年のこと。以来36年の間、このチームでその偉業が達成されたことはなかった。しかし、その最後の事件から2年後の1967年に、まさに寸でのところまで栄光をつかみかけたピッチャーがいたことは、ボストン市民の語り草になっている。その年のレッドソックスのシーズン3試合目の敵地ヤンキースタジアムのマウンドに上がったサウスポーのBilly Rohrは、今回の野茂と同じように彼の最初に登板した試合で、9回裏1アウトを取っていまだノーヒット。次の打者の打ったボールは、ふらふらと上空に舞い上がり、あわやヒットかという球をYastrzemskiが飛びつき、頭からグラウンドに落ちて回転しながらも捕球した球を離さず、ファインプレーを演出して大記録達成への望みをつないだのだった。 何から何まで今回と状況が酷似しているこのあと、しかしRohrは次の打者にヒットを打たれて、ノーヒット・ノーランという大仕事を逃したばかりか、ルーキーとしてメジャー初登板での偉業達成という、これまではもちろんのこと、これからもおよそそんな投手が現れるとも思えない栄冠をその手から逃したのだった。 Lansingのファインプレーで沸き、野茂の最後の一球に固唾を見守る球場の中で、このときとまったく同じ状況であることに嫌な予感を感じていた人は、往年のファンだけではなかったはずだ。その同じグラウンドでおそらくたった一人だけ気付いていたのは、レッドソックスの監督のJimy Williamsだったに違いない。彼はRohrと一緒にプレーした生き証人である。 けれども、歴史は繰り返さなかった。野茂が最後に投じた91mph(146km/h)のこの日一番の速球は、奇しくも5年前のロッキーズとの試合とまったく同じ110球目の、2時間29分というあっと言う間の夢物語の幕を閉じるものとなった。ファインプレーの後に残り1アウトとなって、野茂はRohrには達成し得なかったその偉業を、こともなげに成し遂げてみせた。ルーキーの初登板では成し得なかったが、大リーグ7年目のベテランは、しっかりとその掌中にあった栄冠を離さなかった。 記録達成のその時、グラウンドの中で優勝したかのような騒ぎに沸く選手を、3万5千人のファンで埋められた球場全体が祝福していた。実を言うと、4年前に僕はエンジェルスとの試合を見にこの球場を訪れたことがある。フェンウエイパークの倍はあろうかという球場は、地元のオリオールズを応援するファンでびっしりと埋められていたのを覚えている。そんな雰囲気を知っているだけになおさら、敵の喜ぶ様を祝福するファンの姿に、目の前で繰り広げられている歴史的な瞬間を純粋に楽しみ、それを成し遂げようとする東洋からの開拓者を素直に応援するアメリカ人は、生っ粋の野球好きなんだなという思いを新たにしている。この日、9回の地元オリオールズの攻撃中、審判がボールの判定をしようものなら、驚くことに球場には大ブーイングがこだました。野茂は、敵チームのファンをも味方に付けていた。 いやいや、観客ばかりか、この日の野茂は審判をも味方に付けたかのようだった。大リーグでは今年からストライクゾーンが高めに広く取られるようになり(実際にはルールブックに書かれているゾーンを徹底するようになっただけで、ルールが変わったわけではないが)、次の日のこちらの新聞には、野茂の偉業は新ストライクゾーンの恩恵を被ったような書き方をされていたけれども、テレビのハイライトで奪三振シーンを見ればあきらかに、かなり甘い判定を下されたのは2度や3度ではなかった。 そう言えば、こんなことがあった。 野茂がミルウォーキー・ブリュワーズ時代の2年前に、大リーグ担当のスポーツ記者の間で、大リーグのエースの名に値するピッチャーは誰かという投票があった。その時、メジャーリーグの30にのぼるチームの何百人といるピッチャーの中から、エース候補として名前が挙げられたのは、たったの7、8人に過ぎなかった。そしてそこで挙げられた名前の中に、優勝争いには縁遠い弱小球団で孤軍奮闘する野茂の名前があった。「彼が投げるとき、監督はもちろんのこと、選手の間にも、球場を訪れたファンの間にも、何とも言えない安心感が漂って、何の関係もないこちらにまでひしひしと伝わってくるんだ。そんな雰囲気を持った投手を久しぶりに目にした」という目の肥えた記者達のコメントに、僕は当時いたく感激したものだった。 この日の野茂は、そんな雰囲気に包まれた大リーグのエースだったのに違いない。バックを守る選手に信頼され、敵のファンに応援され、そして最後には審判にも惚れられて。 とかく現代は、実力がものをいう時代であると言われる。なんとなくぎすぎすした世界。でもそんな世の中にあって、実力も大切だけれど、最後にものをいうのは決して「数字」や「地位」ではなく、それを超えて栄冠をかざしてくれるものがあることが、この日あらためて確認されたような気がする。全ての逆境を味方にしてしまうような『人格』こそが、最後にはものをいうということを。 ともすれば、人格なんて関係ないかのような世界に暮らしている「科学」に携わる我々も、やっぱり最後は人格がものをいうに違いないことを肝に銘じて、僕はそんな科学者を目指したいと思う。 さて、1901年に創設され、今年100周年を迎えたレッドソックスは、1918年以来遠ざかっているワールドチャンピオンの座に向かって、幸先良いスタートを切った。今年の野球シーズンが終わったその日、今度は優勝の歓喜の輪の中で「子供のような笑顔」をふりまく野茂をまた見てみたいと願う。 |
 BACK
BACK 
| 旧石器捏造事件の罪 | |
|
ダーウィンが1859年に『種の起源』を著してからおよそ半世紀を経た1912年。ロンドンの南に位置するピルトダウンの砂利採掘場から、ヒトを思わせる頭蓋の破片と類人猿とおぼしき下顎骨の化石が出土した。進化論が定着するにつれ、ヒトは類人猿の形態を残しながらもまず、大きな脳を持つことによってサルから進化したのではないかという、当時の学説とまさに符合する世紀の大発見と騒がれた。 化石の年代判定などで、学者の間で意見が分かれるところはあったようだが、イギリス科学界の権威達はほとんどが、「ピルトダウン人」を人類のルーツと位置づける立場を取るようになった。 その発見から12年後の1924年に、今度は南アフリカで、ピルトダウン人とは逆に下顎骨がヒトのそれに近く脳の容積は小さいという、ヒトと類人猿の特徴を併せ持つ化石が発見され、「アウストラロピテクス・アフリカヌス」と命名された。しかし、ピルトダウン人の存在の大きさと、人類発祥の地をヨーロッパに求めようとする先入観と偏見が、この南アフリカの化石を科学の世界から遠く闇に葬り去ってしまった。 ところが、ピルトダウン人の化石の発見から40年を経た1953年に、世界中の考古学者を愕然とさせる事実が判明し、公表された。なんと、このピルトダウン人の化石は、ヒトの頭蓋骨とオランウータンの下顎骨を組み合わせた偽造品だったのである。ピルトダウン人の歯を電子顕微鏡で調べた結果、それらしく見せるため、研磨剤を使って削った傷痕が観察されたことが、真相解明の糸口となった。 この事件は、アフリカが人類揺籃の地として人々に認知されるまでに大きな時間を要させただけでなく、古人類学の発展に対して大きな損害を加えた許されざるべき犯罪であった。 そして、同様の事件が今また繰り返された。東北旧石器文化研究所の藤村新一副理事長による「旧石器発掘捏造事件」は、世界に対する日本の考古学の信用性を根底から揺さぶるという、なんともやるせない代償を払うこととなった。 アマチュアの考古学愛好家と、東北大、東北福祉大などの専門家がタッグを組んだ異例の研究チームとして1975年に発足した同研究所の前身の「石器文化談話会」は、東北地方で1980年代から相次いで前期旧石器時代の遺跡や石器を発見してきたが、自費で道具をそろえ、発掘を手弁当で支えるという、まさに地道な努力をコツコツと続けてきた組織である。そして、その広範かつ精力的な活動によって次々に成果を挙げ、日本の考古学に大きな影響を及ぼすまでになった。 しかしそれでも、アマチュアの活動ゆえか日本の学会ではなかなかその成果を認めようとせず、長年日本の前期旧石器時代の存在をめぐって大論争が展開されていた。そして最近になって、ようやくこの談話会の成果を認める動きが出て、前期旧石器時代の存在の論争は、決着したと見られていた。そうした流れの末の今回の事件。25年に亘って地道に築き上げてきた基盤は、一瞬にしてまた大きく揺らぎ始めた。 先のピルトダウン人の事件を例に出すまでもなく、今回の捏造事件の考古学に与える影響はあまりに大きい。なにしろ、『石器の神様』と称された藤村氏が発掘に関わった遺跡は、180にも及ぶという。それらすべてについて、再調査を余儀なくされることはもちろんのこと、今や教科書にも掲載されている70万年前に日本にはすでに原人が生活していたという記述の検証を、再び一からやり直すことになる。 そして、今回の事件が目に見えないところでも大なり小なり様々な人に影響を与えるだろう事が、さらに残念でならない。上高森遺跡の近所の子供たちは、日本人の祖先がそこで生活していたことに、70万年の時を超えて胸を踊らせていただろうに。 藤村氏が考古学に興味を持ったきっかけは、小学校2年生のときに裏の畑で見つけた石器が、約5000年前のものだと教師に教わったことだそうだが、同じように、藤村氏のこれまでの数々の発見に心ときめかせた子供たちも居たに違いない。そうした子供たちの思いを踏みにじらないためにも、今回発覚した2つの遺跡以外の場所では不正は行われておらず、これまでの成果が正当なものであったことを、出来るだけ早く検証して欲しいと願う。 |
 BACK
BACK 
| お盆に祖先を偲んで | |
|
日本では今日からお盆が始まった。もっともお盆とは正確には盂蘭盆(うらぼん)といい、7月15日を中心に行う仏教の行事なのだが、今では日本全国で陰暦によって8月に「月遅れの盆」をするのが一般的となり、すっかり社会的行事になっている。ちなみに、この「月遅れ」の行事は我が故郷では確固たるものとなっていて、ひな祭りの桃の節句も端午の節句もすべて「月遅れ」で行われている。だから、6月にこいのぼりがはためく姿を、他の地域(隣町も含む)の人は不思議にあるいはいぶかしく思っていたようだが、そのくせそんな他の地域のお盆は月遅れである。我が故郷の月遅れで首尾一貫として行われている行事の数々に、一本の筋が通ったような胸がすく思いをするのは、僕のちょっとした自慢でもある。 さてお盆のことだけれど、お盆といえば「御墓参り」という図式があるようだが、これまたおかしな話ではある。なぜなら盂蘭盆とは「祖先や亡くなった人の霊を家に迎えて奉る」行事であるからだ。つまり、祖先の霊はお墓にあらず、それぞれの家でこそこれを出迎えるのが筋である。ここでまた我が故郷の自慢をすれば、こうしたしきたりはきちんと受け継がれていて、今日13日は迎え火を焚いて祖先の霊が無事に我が家へと辿り着くように道しるべを立てているし、今日から送り火を焚く16日までの間は、我が家に祖先の霊を奉る御殿をしつらえて、さまざまなお供え物が並んでいる。お盆ともなると方々に散らばった親戚が我が家に集まってくるし、突如家の中に御殿はお目見えするしで、小さい頃には「ご先祖様」の大きさをまざまざと感じたものだった。 ところで、お盆はもちろん仏教の行事だけれど、釈迦が開いた「仏教」という痛烈なるほどの空観(一切皆空という理を体得するために、ものごとを見極めて本質を悟ること)からすれば、お盆とはおかしな行事である。なぜなら、本来の仏教に死霊や霊魂(アニマ)という概念は無く、祖霊思想も無いのだから。そもそも寺がその境内に墓を持つというのも、釈迦が聞いたら嘆いているかもしれない。室町の時代の物語には、仏教のお坊さんがお経を誦んで怨霊を鎮めたという話も多いけれど、それらは新しく興った仏教を日本の土着思想である民間説話を用いて宣伝していたもので、そのあたりから日本の仏教はちょっと道を外し始めたのかもしれない。おまけに、同じ時代に、寺領を持たない寺は食べてゆくために「葬式」というものを始め、死者を弔ってお金を得るという方式を編み出した。もっとも、室町時代ですら僧位僧階を持った正規の僧は「葬式」をつとめたりはしなかったようだが。 このことは、本来の仏教を今に伝える奈良朝や平安初期に創建された寺を見れば合点がいく。斑鳩の法隆寺や東大寺、薬師寺、京都の清水寺には、いずれも境内に墓地はない。 なぜこんなに仏教の本来の姿にこだわるかと言えば、日本の仏教が、仏教本来の姿を必ずしも伝えていないことを知らないがために、つじつまが合わずに言葉に窮したことが何度かあったからである。 ここアメリカでは、その人の「宗教」が何であるかというのは常につきまとう話題である。スペースシャトルに乗り込む宇宙飛行士の記者会見でも、真っ先に聞かれる質問だし、大統領選挙ともなれば自分の宗教観を滔々と語らなければならない。そんなわけで、ランチのときにも幾度となく宗教の話になるのだけれど、カトリック、イスラム教、そしてユダヤ教の信者である我が仲間たちと、仏教の話題になることもしばし。彼らはいわゆる本来の仏教を知識として押さえているものだから、日本の風習について説明すると、「それは仏教の理念からするとおかしくないか」と指摘してくることもある。こんなとき、「敬けんな仏教徒である日本人は非常に少ないから、その実までは知らないものだ」とでも言えば、言葉に窮することも無いのかもしれないが、そこは負けず嫌いの身。あれやこれやと思いつくままに理由を述べてはみるものの、自分でもつじつまが合わなくなってきたりする。まあ、「宗教」という単語すら明治に創作されるまで無かった国の仏教であるから、全く別物の仏教と考えてもらうことにしている。 なんだか、だいぶ脱線してしまったけれど、お盆から連想して今回書きたかったのはタイトルにもあるとおり「祖先」のこと(つまり、まだ本題に入っていないのだけれど)。ちなみに「先祖」とは本来その家系の一番最初の人を指すので、その家系の先代までの人々という意味で「祖先」という言葉を用いている。 「矢部」という名字は、ある統計によれば全国で346番目に多い名前だそうで、人数にして16000人ほどいると言われている。ちなみに一番多い名前の「鈴木」さんや「佐藤」さんは、それぞれ70万人ほどいるそうだ(名前の由来については「YABeT's 今日のImport Data」2月21、22日を参照)。また、日本人の名字の数はおよそ35万種あると言われていて、世界でもまれにみる多様な姓を持つ国民である。 高校生の頃になるが、我が身はどこぞから来たのかと思っていろいろと調べたことがあるのだが、ついぞ正確なことはわからなかった。そもそも、群雄割拠した戦国時代の武将に「矢部」と名乗る者はいないので、たいした血筋の者で「ない」ことは確かである。そんな折り、故郷の天栄村で「村史」なるものが編纂された。この村は実は歴史の舞台にもしばしば登場する場所で、大化の改新で知られる藤原鎌足が訪れたという記録や、嵯峨天皇の病気を治したとされる温泉(ふたまた温泉)、はたまた天皇家ゆかりの人物が眠ると伝えられる前方後円墳が田んぼの真ん中にあったりもする。まあ、そんなお墓だとは知らずに、僕の子供の頃まではそり遊びの格好の場所として使われていたりしたのだが。さて、その1000ページほどの大部4巻からなる「村史」をあるとき見るともなく眺めていたら、「矢部」なる人物の記述があることに気がついた。 それによれば、「矢部」氏は須賀川に居城を構える二階堂氏の筆頭家来であることがわかった。二階堂氏は、源頼朝が奥州征伐に出かけた際に平泉の藤原卿にあった二階建ての建造物に驚嘆し、それをまねて鎌倉の鶴ヶ岡八幡宮の守り堂を二階建てにしたことで、その二階堂の責任者となった工藤氏が改名した名前である。その後、足利将軍の時代に現在の福島の須賀川を中心とする岩瀬郡一帯を拠点にするようになった(天栄村は岩瀬郡にある)。その筆頭家来ということは、「矢部」氏もまた二階堂氏と共に鎌倉から移ってきた人々であろうか。その後、二階堂氏は伊達政宗が勢力拡大のため南下してきた際に滅亡のうきめにあった武将であるが、その筆頭家来である「矢部」氏は、その滅亡からまぬがれ、いまこうして僕があるのかもしれない。 余談だけれど、伊達政宗は須賀川城を落とした後も更に南下を続け、我が天栄村にまで到達した。しかし、我が故郷に居を構えた「飯豊(いいとよ)城」「小川城」「大里城」はよくこれに抗戦し、政宗は策に窮したと伝えられている。そうこうするうちに、豊臣秀吉から小田原城攻めの大号令が下り、これらの城のうち大里城をついに落とすことなく小田原に向かっている。伊達政宗が攻めて陥落させることが出来なかった城は、この天栄村の大里城だけである。ちなみに「飯豊城」は、後に徳川光國(水戸黄門)に仕えた佐々介三郎(すけさん)の祖父が治めていた城。すけさんは架空の人物と思っている人も多いが、大立ち回りをしたかどうかはともかく、徳川光國の大事業であった『大日本史』を編纂するにあたり、城内にとどまる光國に代わって諸国を歩いて『大日本史』の資料集めを行った学者として歴史に名を残している。このすけさんの諸国漫遊は、後に漫遊記として脚色され、ご存じ「水戸黄門」として今も語り継がれている。というわけで、すけさんの家系は天栄村出身なのである。もっとも伊達政宗の攻撃を受けて、飯豊城主の佐々氏は潰走し秋田に逃れ、徳川の時代に水戸から佐竹氏が秋田に配置されたのに伴って佐々氏は水戸に入り、そこで徳川に仕え、介三郎はそこで生まれているので、彼自身と天栄村の関係は無いといえば無いのだが。 さて、なんとなく「矢部」のルーツがわかったのだが、それでも釈然としたものではないので、あるとき家紋からそのルーツを探ってみようと思い立った。我が家の家紋は「丸に桔梗」というものである。桔梗は、むかし花を一輪、神や仏に捧げて吉凶を占ったことに由来する名前で、運命を暗示する花とされている。そのせいか、桔梗を家紋にした武将には運命的な生涯を送った人物が多い。明智光秀、太田道潅、加藤清正など。 桔梗紋は、美濃に勢力があった土岐一族の家紋として知られている。 土岐氏は、源頼光、その子頼国がともに美濃守となり、頼国の曽孫光信のときに美濃国土岐郡土岐卿に居住して、はじめて土岐氏を名乗った。源頼光は清和天皇の子孫で、いわゆる清和源氏である。土岐氏は、後に秀吉、家康に仕えて徳川旗本として家名を存続させているが、斎藤道三に国を盗られ、美濃を追われたその家である。この土岐氏からは、明智、揖斐、原、蜂屋、土居、などの諸氏が分かれているが、残念ながら「矢部」という分家はない。 しかし、土岐氏の系譜からそのルーツを探すことは出来なかったが、ルーツ探しの手だてが途切れたわけではない。実は、先に挙げた武将の中で桔梗を家紋とする加藤清正は、この土岐氏一族ではないので、こちらにゆかりがあるとも考えられるからだ。5歳の頃から秀吉のもとで養育され、数々の功績により熊本城を築くまでに出世する加藤清正だが、藤原北家道長流という出自は後の創作であると考えられていて、秀吉と同じ尾張国中村の農民の子というのが有力な説である。出世をする段階で、故郷に近い美濃を代表する武将である土岐氏の「桔梗」を家紋として使っていたのだろう。この加藤氏は、その類まれな才能は一代限りのものであったようで、その息子が跡を継ぐと改易を命じられ、熊本は細川氏のものとなっている。 桔梗紋を使用した加藤清正と「矢部」のつながりは・・・あるのだ。現在の熊本県との県境にある福岡県の八女郡矢部村である。矢部川の源流を抱えるこの村は、古くから矢篠竹が密生する地域で、矢作りをなりわいとする家が多く、「矢の部」と呼ばれていたことに由来してこの名前がついたという。この地域は、加藤清正の治めていた肥後の国であり、猛将であった清正がこの地域の矢を気に入って、現地の「矢部」氏を家来とし、この地の人々に自分の「桔梗」紋を家紋として与えたと考えても不思議ではない。そうなれば、同じ桔梗紋を持つ我が家の祖先は、この地域の出身である可能性が高いことになる。 もっとも、加藤清正が肥後全土の領主となるのは、慶長五年(1600年)の関ケ原の直後であるから、先の二階堂氏の家来であった「矢部」氏とは時代が重なってしまい、つながりを説明するのは少々骨が折れる。九州の同門であった二階堂氏の家来である「矢部」氏が、故郷の同朋が加藤清正にあやかって「桔梗」を家紋として使い始めたことを伝え聞いて、同じく使い始めたと考えられなくもないが。 というわけで、祖先を偲ぶというよりは「矢部家のルーツ探し」のような話になってしまったけれど、お盆ということで、まだはっきりと確定はできない我が家の祖先に思いを馳せてみた。 |
 BACK
BACK 
| 協力するということ | |
|
5月17日付のWashingon Postにこんな記事が載っていた。「Japanese Leader Trips Over His Tongue(日本のリーダー(首相)が自分の言葉によろめく)」という記事だ。これは、先日の森首相の「日本の国、まさに天皇を中心とする神の国・・・」という発言を取り上げたもので、「宗教分離をうたった日本国憲法をないがしろにした、まるで第二次世界大戦以前に逆戻りしたかのような発言」と厳しく批判している。その後どのように首相が釈明したのか知らないけれど、「日本のリーダー」のその認識たるや・・・なんだか呆れるというよりは悲しくなってくる。 こんな発言を受けて連立与党となっている公明党は果たしてどんな対応を取るのかと思えば、別に批判するでもなく平然としている。これにはさらに驚かざるを得ない。なぜなら、公明党の支持母体である創価学会の初代会長は、戦争中に政府が伊勢神宮の神礼拝受などを強要したのを拒絶したために獄死した歴史があるからだが、連立与党としての協力を遵守するがために、依って立つべき道理をまで曲げなければならないとは。 協力すると言えば、台湾に陳総統が誕生して中国と台湾の新しい関係が、果たして険悪な対立関係から協力関係へと改善していけるかどうか、おおいに注目されている。そんな中、先日の新総統の就任を祝う晩餐会で、陳総統は料理を請け負う円山大飯店のシェフに要望を出したそうだ。「新しい全民政権(人民の、人民による、人民のための政治)の門出を祝う新しいメニューを」と。その結果、これまでの豪華な料理に代わって、庶民の食べる台湾の味が並んだそうだ。そして最後に運ばれてきたデザートは「イモのカステラ」。円山大飯店の名物「アズキのカステラ」のアズキをサトイモとサツマイモにしたカステラである。台湾の人たちは、台湾がサツマイモのような形をしていることから、自分たちを「サツマイモ(蕃薯)」と呼び、中国大陸出身者を「サトイモ(芋頭)」と呼ぶことから、このカステラは大陸出身者と台湾の人々の融和を表わした料理ということになろうか。両者の協力を願う思いが、ひしひしと伝わってくる。 一方、とかく競争社会だと考えられている科学の世界でも、対象が細分化し膨大な知識を必要とする現代科学において、今や協力は欠かせない。特に、国を超えての共同研究は年々その割合を増している。しかし、こと日本に限ってみてみると、世界的なそうした風潮に乗り遅れている姿が浮き彫りにされている。先日発表された過去5年間の科学論文の国別の発表数によれば、日本はアメリカに次いで2番目に多い論文を世界に向けて発表しているけれど、世界のほとんどの国で国際共著論文が論文全体に占める割合が25〜40%であるのに対して、日本は15%と特に低いことが指摘された。主たる原因が言葉であることは明らかだろうが、国際貢献に直結しているともいえる科学の分野で遅れをとらないためにも、競争するばかりでなく、国際的な共同研究にもっと目を向けるべきだと思う。国際的な共同研究には、自分の道理を曲げる必要もなく、それまでの対立関係を修復する必要もない。さらには、誰に気兼ねすることもなく、誰の許可もいらない。国際化はこんなところでも進んでいる。 |
 BACK
BACK 
| 弘山晴美選手のシドニー五輪への夢がかなって | |
|
今年1月の大阪国際マラソンで、日本歴代3位という記録を出しながら、ルーマニアのシモン選手に勝負で負けたことが響いて、弘山晴美選手はシドニーオリンピックのマラソン代表選考会で落選した。彼女のマラソン代表挑戦は、昨年秋の1万メートルの代表内定を振り払ってのものだっただけに、その悔しさはいかばかりだったろうか。 案の定、1万メートルの代表獲得に目標を切り替えてからも、精神的な落ち込みでほとんど練習が出来ない状態だったそうだ。彼女はぽつり「もうやめたい」と夫でもあるコーチにもらしたそうだ。 「僕に言葉をかけてほしいのだ、とわかったが、わざとらしい激励はあえてしなかった」(毎日新聞)とは当のコーチの弁。ひたすら彼女を信じて意欲の回復を待ったという。 また、マラソンの代表選考で弘山選手の落選の原因となったライバルであるシモン選手は、食事をする機会を設けるなどして温かい言葉をかけ続けたそうだ。「絶対にあきらめないで」と。 そして5月7日のシドニーオリンピックの陸上の日本代表選考会を兼ねた水戸国際大会で、弘山選手は2位に大差をつけて1万メートルで優勝。見事代表の切符を手にした。 言葉をかけない優しさと、言葉をかけ続けた優しさ。正反対に見える行為の陰にあるのは、もちろん彼女のまわりを取り囲む人たちの、彼女を思いやる気持ちである。 現在首相となっている森さんがまだ自民党幹事長だった頃、陳健駐日大使に中国大使館に招待され、極上のフカヒレスープでもてなしを受けたそうだ。森さんは、あまりのおいしさに皿を持ち上げて、残ったスープを飲み干してしまったという。しかし、ご飯以外の皿や茶わんに直接口をつけないのが中国のマナー。森さんの行為は、明らかにこのマナーに反していることになる。 けれども、中国の外交官たちはけげんな顔をするようなことはなかった。なぜなら、空になって食卓におかれた皿が、この料理に対する最高の賛辞を示していたからである。以来、陳大使はこのフカヒレスープで日本人のゲストをもてなすたびに、自分から皿を持って「森さんに教わりました」と残ったスープも飲むように勧めているそうだ。 言葉として表に現れた形や、マナーという無難な決まりごとに従うことによって、人々は動かされるのではない。その行為の基となっている、その人の思いによって、人は動かされるのである。そして、そうした周りの人たちの思いに報いるためにも、弘山選手や陳大使のように、素直にその気持ちを感じとることの出来る人でありたいと願う。 復活した弘山選手の表彰台の上でさらに輝く姿が、きっと今年のオリンピックで見られるに違いない。乗り越えた壁の大きさに見合うプレゼントが、未来に待ち受けているはずだから。 |
 BACK
BACK 
| 世界のなかの日本 | |
|
アメリカという国で毎日の生活を送っていると、世界という尺度でものごとを考えるのにそう苦労をしなくて済むのは、ありがたいものだ(たしかに、毎日文句ばかり出るときもあるのだが)。街には世界中から集まった外国人があふれ、アメリカ人と言えどもその肌の色も風貌も言葉さえも違う様々な人々が、何の違和感もなく普通に生活している。そして、それぞれの人種の文化、民族の慣習を尊重しながら、ほんわりと調和した社会を作っている。 一方、日本に目を転じてみると、この時代にこれほど外国人の姿を見るのが難しい国も無いのじゃなかろうかと思うほどに、日本人一色の国である。まあ、おかげで意思の疎通をはかるのに何の苦労もいらないという独特の社会を作り出し、世界に誇る日本独自の文化も生まれている。しかし、あまりに純血にこだわっていると、この混沌としたご時世に、果たして生き残っていけるのだろうかと、不安も広がってくる。もちろん日本人という範疇には、大和民族以外にもアイヌ民族も朝鮮民族も含まれているのだが、日本語を操ることの出来ない人々がコミュニティーを形成している地域というのは、出稼ぎで入国している一部の日系ブラジル人やイラン人以外あまり聞かないような気がする。 日本には、戦後の高度経済成長を支えるために、猫の手も借りたいほどに人手を必要としたにも関わらず、一貫して他民族の大量移民を認めてこなかった歴史がある。僕は歴史家でも政治家でもないから、素人の当て推量を笑っていただいて構わないが、これは江戸時代に貫かれた「鎖国」時代の日本人の気質が、知らず知らず人々の魂の根底に宿っていたのではないかという気がしている。つまり、江戸時代には外国人に(アイヌ人にさえ)日本語を教えることを禁じ、日本語を理解するのは日本人だけという政策を取ることによって、日本からの情報の流出を食い止めていたのだけれど、その根本には、外国人といういわば異質物への日本社会の拒絶反応が、漠然とした不安をかきたてていたのだと思う。 現在ちまたでは声高に国際化が叫ばれ、自分たちも日本人である前に同じ地球に住む人間だという意識が高められようとしているが、実際のところは、普段の生活のレベルでそれを感じることはないのが正直なところだろう。誰もが、知らず知らず外国と日本は全然違う次元のものであるように感じているに違いない。 日本人のはしくれとして、それを誰のせいにするつもりもないし、自分だけは違うぞと胸を張って国際人ぶるつもりはない。ただ、アメリカのような混沌とした民族のるつぼである社会に身を置き、「多様」である価値観を目の当たりにしている者として、そういう社会が世界には存在し、そしてそれが今や世界の主流になろうとしていることを伝えたいだけなのだ。 たとえば、オランダのアムステルダム市では、人口の実に60%が外国人(東南アジア人、アフリカ人が主)であるが、彼らへの差別的な制度は一切ないし、選挙権すら彼らに与えられている。また、イタリアの大都市にはアフリカからの違法移民者が溢れかえっているけれども、社会はそれを拒否することもなく、彼らを当然の働き手として受け入れているのだ。彼らの多くは、かつて自分たちの同朋がアメリカや南アメリカに多く進入していったのだから、今度は自分たちが受け入れる番なのだと考えているそうだ。 一方、明治維新以来、西洋に追いつき追いこせを合い言葉に、外国人を仲間としてではなく敵として目標に掲げていた日本人は、勤勉さと手のこまやかさを武器に、容赦なく外国に製品を売り付け、そこで生活する人々の職を奪ってきた。これは、文化的な背景をまったく抜きにして短期間で欧米に並ぼうとしたのだから、ある意味では仕方のないことかもしれないが、「自由経済主義」をイデオロギーとしてではなく、ツールとしてしか自分の物に出来なかったことを示しているのだろうし、世界の一員としての認識が大きく欠けていたことを素直に認めなければならないのかもしれない。すでにそのつけは、世界中のさまざまな場所で多くの日本人が払わされてきているが。 日本も、思いきって外国人の移民を受け入れるぐらいの気概が必要な時期なのではないか。昨今、少子化が問題にされて久しい。これからの人手不足は、まさに外国人に補ってもらうという考え方が、かならずしも突飛だとも思えない。もちろん、今すぐにといってもただ混乱を招くだけなのは、火を見るよりも明らかだけれど、自分のまわりに異文化からやって来た人がいる事が、決して不自然なことではないということを意識する時代になっているのかもしれない。 世の中、様々な人がいるからおもしろい、と僕は常々口にしている。どうせおもしろがるのなら、わずかの違いを日本人どうしで見つけ合うのではなく、なんでこんなに違うのだろうかという驚きもまた、楽しく感じられる暮らしこそが、国際化なんだろうと思う。日本の外に世界があるのではなく、世界の中に日本があるのだから。 |
 BACK
BACK 
| 世界を結ぶインターネット | |
|
最近、あちらこちらでハッカー(もともとのコンピューター用語で「ハッカー」というのは破壊工作をする人に対して使われていたわけではないので、昨今の被害を招いている犯人に対しては本来「クラッカー」という用語の方が適当だと思うけれど、今ではハッカーと呼ぶアメリカ人も多いので、ここでもハッカーと呼ぶことにする)の被害に遭ったという話を耳にすることが多くなった。それだけ、インターネットがメジャーなシロモノになってきたということだろうけれど、中には、この手の攻撃に対しては専門家をずらっと並べて万全の対策を誇っている、アメリカの国防総省やヤフー社のネットワークを麻痺させるなんていう、悪質なものも最近話題になった。 漠然とした得体の知れないものほど怖いものはない。そこで、こうしたネットワークの混乱を招く所業とは、いったいどのようにしているのかというのをちょっと調べてみた・・・決してまねをしてハッカーになろうというつもりではないけれど。 例えば、先日のヤフーが襲われた際の攻撃の種類は、「サービス拒否(Denial of Service)」攻撃と呼ばれるもので、ターゲットとなる企業のネットワークを何かで詰まらせようとする手法でネットワークを破壊するものだそうだ。こうした攻撃は、ある程度匿名で実行できる上、技術的熟練がほとんど要らないため、最近特に流行しているもので、その攻撃を実行するソフトの名前から「スマーフィング」「フラッギング」などの種類がある。 スマーフィング攻撃の仕組みは、攻撃者が一連の「エコー」応答要求を送り出し、その要求が自分自身のコンピューターから来たもののように見せかけるというもの。その結果、応答は増幅されてしまい、ターゲットとなったネットワークは圧倒されてしまう。しかし、この手の攻撃に対する防御策はよく知られていて、管理者さえしっかりしていれば防ぐことは出来る。単に、コンピューターがエコー要求を無視するように設定変更すればよいだけであるから。現にスマーフィングによる攻撃は、1997年に有名になって以来、現在では50%ほどに減少しているそうだ。 しかし敵もさる者。現在最もやっかいだといわれているプログラムは「トライヌー」「TFN」と呼ばれるもので、ヤフー社が襲われたのはまさにこの攻撃によってであった。この設計は驚くほど巧妙な上、きわめて単純。1つのサイトが増幅攻撃を始めるのではなく、大規模なネットワークが協調してより破壊的なやり方でターゲットを攻撃するというもの。具体的には、マスターの「ハンドラー・コンピューター」が、攻撃開始時間になるとあらかじめトライヌーやTNFのデーモンがインストールされた「エージェント」マシンのネットワークに信号を送り、一斉に攻撃が始まる。 これへの対処は、始まってしまえばもうどうしようも無いのだが、世界中のネットワークの管理者が協調すれば簡単に防ぐことができる。つまり、コンピューターにトライヌーやTNFのバイナリコピーがしまい込まれていないかどうかを、毎日探す作業をするだけで防ぐことが出来る。 ところがここに来て「TFN2000」やら「シュタッヒェルドラート」などというプログラムが現れた。エージェントとなるコンピューターにしまい込んだプログラムが、管理者に見つけられないように暗号化された通信を用いているというシロモノ。いやはやまったくもってあきらめの悪い人たちである。 インターネット無しでは、仕事も生活も出来ないような暮らしをしている僕のような身には、ハッカーによる攻撃はまさに重大な事件である。ハッカーへの対抗策を講じる方々には、本当に頑張ってもらいたいものだが、どうやら世界中のネットワーク運営者が、一致団結して事を運ぶことが最大の防御策のようだ。世界をつなぐインターネットはまた、世界の人をつなぐネットワークであり、結び付きを強める役割を担っていくことになるのかもしれない。いっそのこと、強固な関係を作り上げて、ハッカーの入る余地もないものができ上がることを期待しながら、今日も交信。 |
 BACK
BACK 
| 2000年というエネルギー | |
|
日本の国技である相撲を支える日本相撲協会といえば、1500年に亘る伝統文化を守ろうとするが故に、様々なしきたりにしばられた頭の固い集団であるというのが通り相場である。毎場所の初日に行われる土俵上の理事長あいさつは、その形式ばった体質を象徴するようなセレモニーで、事務局が作成したものを理事長が目をしばたたかせながら読み上げ、読み終わっても礼儀を知る日本人ですら拍手もしないというのが通例であった。 しかし、先日の武双山の優勝で幕を閉じた初場所の初日あいさつでは、その伝統を時津風理事長自らが打ち破り、初めて自分で原稿を書き、己の言葉で観衆に語りかけたそうだ。そうした型破りともいえる切々とした言葉を目の当たりにした観衆からは、通例を破っての拍手が湧いたという。 また、型破りといえば、イギリスのエリザベス女王が私的な資金10万ポンド(約1800万円)を使って、インターネット関連の新会社に株式投資を行ったことが伝えられた。王室が利殖目的で民間企業に投資するのはまさに前代未聞であるが、女王が金儲けをして悪いという法律はないわけだから、これも時津風理事長の自前のあいさつとなんら変わらない出来事なのかもしれない。 もうひとつイギリスから。日本の相撲に匹敵するイギリスの国技といえばサッカーであるが、1905年創立の名門チーム、チェルシー(ロンドン)の試合で、前代未聞、型破りな事件が先日起きた。なんと、11人の先発メンバーおよび監督までが全員外国人(イギリス人以外)だったのである。なんともはや、イタリア人監督のビアリさんも思いきったことをするものだが、持てる力をすべて出し切ってベストの試合をするということを突き詰めると、結局はこういうことになるのだろう。これぞ「国際化」である。 2000年となって一カ月。伝統を打ち破る様々な出来事が、あちらこちらから聞こえてくる。これだけ世間が「新しい時代」と盛り上げてくれるのだから、それを利用しない手はない。古き良き伝統をないがしろにすることなく、けれども伝統という言葉にしばられることなく、自由な発想で新しい時代を切り拓いていきたいものだ。不思議な力を持つ「2000年」にあやかって。 |
 BACK
BACK 